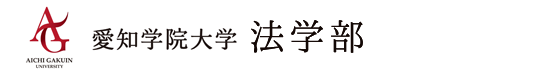法律研究会
宗教法制研究所が毎年開催している「法律研究会」の報告内容をご紹介します。
ページ内目次
- 令和4年度第1回法律研究会(報告者:林昌宏)
- 令和3年度第1回法律研究会(報告者:波多江悟史)
- 令和2年度第1回法律研究会(報告者:永岩慧子)
- 令和元年度第1回法律研究会(報告者:三上正隆)
- 平成30年度第1回法律研究会(報告者:黒野葉子)
- 平成28年度第1回法律研究会(報告者:髙橋洋)
- 平成26年度第2回法律研究会(報告者:野村健太郎)
- 平成26年度第1回法律研究会(報告者:佐藤啓子)
- 平成25年度第1回法律研究会(報告者:小林明夫)
- 平成24年度第1回法律研究会(報告者:前田太朗)
- 平成22年度第2回法律研究会(報告者:村上康司)
- 平成22年度第1回法律研究会(報告者:三上正隆)
- 平成21年度第2回法律研究会(報告者:府川繭子)
- 平成21年度第1回法律研究会(報告者:鈴木慎太郎)
- 平成20年度第2回法律研究会(報告者:武田典浩)
- 平成20年度第1回法律研究会(報告者:石田倫識)
- 平成19年度第3回法律研究会(報告者:伊藤栄寿)
- 平成19年度第2回法律研究会(報告者:鈴木伸智)
- 平成19年度第1回法律研究会(報告者:神田桂)
令和4年度第1回法律研究会(報告者:林昌宏)
| 日時 | 2022年10月26日(水)15時00分~16時30分 |
| 報告テーマ | 地方分権的な制度の導入は、何をもたらすのか ――現代日本の港湾整備事業を踏まえて―― |
| 報告者 | 林昌宏(政治学) |
本報告は、制度配置と制度作動に着目しながら、地方分権的な制度の導入が何をもたらすのかを明らかにしようとしたものになる。分析対象は、1950年の港湾法の制定を契機として地方分権的な制度が確立され、そのもとで実施され続けてきた日本の港湾整備事業(1950~2010年代)と、そちらにおける行政体制である。
日本の港湾整備事業に関する先行研究は、港湾整備事業をめぐって国と地方自治体が強調しながらそれを実施しているという捉え方、もしくは地方自治体が国のコントロール下にあるという見解が一般的であった。これらに対して、本報告は、政治学・行政学の知見を援用しつつ、港湾を管理・整備しているのは、①1950年に制定された港湾法に基づき地方自治体であること、②港湾整備事業をめぐり中央政府(特に運輸省)は地方自治体に統制を試みているが、必ずしも実現できてはいないこと、③運輸省以外の省庁や政権党、海運業界、経済団体、地域住民をはじめとするアクターも港湾整備事業に関与し、それらの意向が反映されていること、これらを主張の軸とすることにした。また、港湾整備事業をめぐって、地方自治体はどのように自律的かつ戦略的に活動するのか、中央-地方政府間関係あるいは地方-地方政府間関係はいかなる姿となっているのか、官民関係は政策帰結にどのような影響を及ぼすのかを分析課題に設定した。
まず、事例分析の前提として明治期からアジア・太平洋戦争敗戦までの港湾管理・整備の特徴を確認した。近代日本の港湾整備事業の実施主体は、大蔵省、内務省が中心であった。敗戦後のGHQによる占領改革の一環として、1950年に港湾法が制定され、地方自治体が港湾管理権を取得することになった。ただし、港湾管理権の地方自治体への移譲は運輸省にとって受け入れ難い措置であり、それがその後の港湾整備事業をめぐる中央-地方政府間関係の規定要因となっていることを指摘した。その後、港湾をめぐる諸制度の運用をめぐって試行錯誤が続けられていく中で、日本は高度経済成長期および「第二の黒船」と称されたコンテナ化の時代を迎えていくことになる。
つづいて、大阪湾と瀬戸内海東部の港湾を事例に、その整備事業をめぐる地方-地方政府間関係を分析した。神戸港の管理者である神戸市は、1950年代以降に港湾の大規模化やコンテナ化を積極的に進め、現代日本の港湾整備事業のフロントランナーとなった。そして、大阪港とその管理者である大阪市、尼崎西宮芦屋港とその管理者である兵庫県が、それへのキャッチアップを試みていた。ただし、尼崎西宮芦屋港の大規模化は、住民運動や経済環境の変化もあって失敗に終わった。また、兵庫県が注力した姫路港や東播磨港の整備は、播磨工業地帯の躍進を支え、他方で阪神工業地帯の凋落の要因の一つを生み出していた。
第3に、外貿埠頭公団と名古屋コンテナ埠頭株式会社を事例に、中央-地方政府間関係を分析した。コンテナ埠頭を整備するための特殊法人である外貿埠頭公団の設立をめぐって運輸省と地方自治体は衝突を繰り返すことになった。さらには、中央政府内部での軋轢も生じ、それが公団設立に様々な影響を及ぼしていた。同公団の廃止をめぐっては、地方自治体と海運業界の軋轢が表面化し、最終的には政治決定で決着させることになった。名古屋コンテナ埠頭株式会社の事例では、またしても地方自治体と運輸省の衝突が発生し、最終的には地方自治体側に有利な形で決着が図られている。地方自治体は、国とりわけ所管官庁の運輸省にとって「従順ならざる存在」であったのである。
第4に、1990年代の東アジア各国の港湾の台頭と国内の地方港のコンテナ化の状況、中央省庁再編による国土交通省の誕生(2001年)、スーパー中枢港湾政策や国際コンテナ戦略港湾政策に象徴される国土交通省主導による港湾の国際競争力回復に向けた動きを取り上げた。これをもとに近年の港湾整備事業をめぐる中央-地方政府間関係は、中央政府が優位なそれと、地方政府が自律性を発揮しようとするそれの二層構造になっている点を指摘した。
最後に本報告は、地方分権的な制度の導入によって、地方自治体は自律的に活動し、他のそれらと競合しながら港湾の大規模化を進めていたことや、垂直的でない中央-地方政府間関係あるいは一枚岩でない中央政府の状況が生み出され、それが政策帰結に多大な影響を及ぼしていたことを結論として提示した。そして、複雑で不安定、不確実なパワーバランスのもとで政策決定、政策帰結の導出が繰り返されてきたことが、今日の日本の港湾整備事業の先行きを不透明にしていること、そしてその詳細を明らかにすることを今後の課題に位置付けた。
日本の港湾整備事業に関する先行研究は、港湾整備事業をめぐって国と地方自治体が強調しながらそれを実施しているという捉え方、もしくは地方自治体が国のコントロール下にあるという見解が一般的であった。これらに対して、本報告は、政治学・行政学の知見を援用しつつ、港湾を管理・整備しているのは、①1950年に制定された港湾法に基づき地方自治体であること、②港湾整備事業をめぐり中央政府(特に運輸省)は地方自治体に統制を試みているが、必ずしも実現できてはいないこと、③運輸省以外の省庁や政権党、海運業界、経済団体、地域住民をはじめとするアクターも港湾整備事業に関与し、それらの意向が反映されていること、これらを主張の軸とすることにした。また、港湾整備事業をめぐって、地方自治体はどのように自律的かつ戦略的に活動するのか、中央-地方政府間関係あるいは地方-地方政府間関係はいかなる姿となっているのか、官民関係は政策帰結にどのような影響を及ぼすのかを分析課題に設定した。
まず、事例分析の前提として明治期からアジア・太平洋戦争敗戦までの港湾管理・整備の特徴を確認した。近代日本の港湾整備事業の実施主体は、大蔵省、内務省が中心であった。敗戦後のGHQによる占領改革の一環として、1950年に港湾法が制定され、地方自治体が港湾管理権を取得することになった。ただし、港湾管理権の地方自治体への移譲は運輸省にとって受け入れ難い措置であり、それがその後の港湾整備事業をめぐる中央-地方政府間関係の規定要因となっていることを指摘した。その後、港湾をめぐる諸制度の運用をめぐって試行錯誤が続けられていく中で、日本は高度経済成長期および「第二の黒船」と称されたコンテナ化の時代を迎えていくことになる。
つづいて、大阪湾と瀬戸内海東部の港湾を事例に、その整備事業をめぐる地方-地方政府間関係を分析した。神戸港の管理者である神戸市は、1950年代以降に港湾の大規模化やコンテナ化を積極的に進め、現代日本の港湾整備事業のフロントランナーとなった。そして、大阪港とその管理者である大阪市、尼崎西宮芦屋港とその管理者である兵庫県が、それへのキャッチアップを試みていた。ただし、尼崎西宮芦屋港の大規模化は、住民運動や経済環境の変化もあって失敗に終わった。また、兵庫県が注力した姫路港や東播磨港の整備は、播磨工業地帯の躍進を支え、他方で阪神工業地帯の凋落の要因の一つを生み出していた。
第3に、外貿埠頭公団と名古屋コンテナ埠頭株式会社を事例に、中央-地方政府間関係を分析した。コンテナ埠頭を整備するための特殊法人である外貿埠頭公団の設立をめぐって運輸省と地方自治体は衝突を繰り返すことになった。さらには、中央政府内部での軋轢も生じ、それが公団設立に様々な影響を及ぼしていた。同公団の廃止をめぐっては、地方自治体と海運業界の軋轢が表面化し、最終的には政治決定で決着させることになった。名古屋コンテナ埠頭株式会社の事例では、またしても地方自治体と運輸省の衝突が発生し、最終的には地方自治体側に有利な形で決着が図られている。地方自治体は、国とりわけ所管官庁の運輸省にとって「従順ならざる存在」であったのである。
第4に、1990年代の東アジア各国の港湾の台頭と国内の地方港のコンテナ化の状況、中央省庁再編による国土交通省の誕生(2001年)、スーパー中枢港湾政策や国際コンテナ戦略港湾政策に象徴される国土交通省主導による港湾の国際競争力回復に向けた動きを取り上げた。これをもとに近年の港湾整備事業をめぐる中央-地方政府間関係は、中央政府が優位なそれと、地方政府が自律性を発揮しようとするそれの二層構造になっている点を指摘した。
最後に本報告は、地方分権的な制度の導入によって、地方自治体は自律的に活動し、他のそれらと競合しながら港湾の大規模化を進めていたことや、垂直的でない中央-地方政府間関係あるいは一枚岩でない中央政府の状況が生み出され、それが政策帰結に多大な影響を及ぼしていたことを結論として提示した。そして、複雑で不安定、不確実なパワーバランスのもとで政策決定、政策帰結の導出が繰り返されてきたことが、今日の日本の港湾整備事業の先行きを不透明にしていること、そしてその詳細を明らかにすることを今後の課題に位置付けた。
令和3年度第1回法律研究会(報告者:波多江悟史)
| 日時 | 2021年12月22日(水)15時00分~16時30分 |
| 報告テーマ | イタリア公共放送RAIのガバナンスについて |
| 報告者 | 波多江悟史(憲法) |
近年、グローバルIT企業が提供するプラットフォームを通じて様々な情報が発信される中で、インターネットにおける公共放送の活動をどのように保障し統制するかが問題となっている。そこで、本報告では、こうした問題について、イタリア公共放送RAIを素材として検討する。
イタリアでは、2015年に成立したRAI改革法が、インターネット社会におけるRAIの任務遂行を確保するため、RAIの経営の効率性と議会からの独立性を強化している。さらに、2018年にRAIが経済財務省との間で締結した事業契約書は、人間の発達、権利、個人の能力の促進という観点と、社会の構成、強化、成長の促進という観点を強調し、具体的には、マルチメディア・プラットフォームを通した番組配信や、事実の真実性・文脈性、情報の客観性・公平性の確保などを定めている。
もっとも、憲法裁判所は、公共放送の指導機関は行政権の排他的・支配的意見を直接的・間接的に反映してはならないこと、むしろ放送を規制し監督する権限は議会にあることを強調してきた。しかし、2015年RAI改革法は、取締役7名のうち4名を政府与党が選出することを可能とするだけでなく、政府が大半の株式を保有することを前提として、株主総会の提案に基づき取締役会が選任する代表取締役に対し広範な権限を集中させている。そのため、2015年法は憲法に違反すると批判されている。
しかし、2015年法は議会によるRAI支配に対処するものでもあったため、RAIに関する議会の規律権限を強調したとしても、国家によるRAI支配という問題が解決されるわけではない。こうした観点から、近年では、RAIのガバナンスについて、公益法人を設立することによって、政治権力と経営機関の間に障壁を設営するという見解が有力に支持されている。この見解によれば、公益法人は、RAIの全株式を取得した上で、専門性と独立性を併せ持つ5名から10名の評議員によって組織される評議員会に基づき、RAIの取締役を選任する権限、政府との間で協約書を締結する権限、RAIとの間で事業契約書を締結する権限などを有することになる。
さらに、2015年法は、代表取締役の強力なリーダーシップの下、公共放送から公共メディアへの転換を図っているが、こうした手法もEU構成国では標準的なものではない。むしろ、イギリスにおけるPublic Value Testや、ドイツにおけるDrei-Stufen-Testのように、近年では公共メディアのあり方に関する社会的コンセンサスの形成が重視されている。こうしたイタリアの議論からは、公共メディアについても国家に対する距離の確保と社会的コンセンサスの形成が重要となることを読み取ることができる。
イタリアでは、2015年に成立したRAI改革法が、インターネット社会におけるRAIの任務遂行を確保するため、RAIの経営の効率性と議会からの独立性を強化している。さらに、2018年にRAIが経済財務省との間で締結した事業契約書は、人間の発達、権利、個人の能力の促進という観点と、社会の構成、強化、成長の促進という観点を強調し、具体的には、マルチメディア・プラットフォームを通した番組配信や、事実の真実性・文脈性、情報の客観性・公平性の確保などを定めている。
もっとも、憲法裁判所は、公共放送の指導機関は行政権の排他的・支配的意見を直接的・間接的に反映してはならないこと、むしろ放送を規制し監督する権限は議会にあることを強調してきた。しかし、2015年RAI改革法は、取締役7名のうち4名を政府与党が選出することを可能とするだけでなく、政府が大半の株式を保有することを前提として、株主総会の提案に基づき取締役会が選任する代表取締役に対し広範な権限を集中させている。そのため、2015年法は憲法に違反すると批判されている。
しかし、2015年法は議会によるRAI支配に対処するものでもあったため、RAIに関する議会の規律権限を強調したとしても、国家によるRAI支配という問題が解決されるわけではない。こうした観点から、近年では、RAIのガバナンスについて、公益法人を設立することによって、政治権力と経営機関の間に障壁を設営するという見解が有力に支持されている。この見解によれば、公益法人は、RAIの全株式を取得した上で、専門性と独立性を併せ持つ5名から10名の評議員によって組織される評議員会に基づき、RAIの取締役を選任する権限、政府との間で協約書を締結する権限、RAIとの間で事業契約書を締結する権限などを有することになる。
さらに、2015年法は、代表取締役の強力なリーダーシップの下、公共放送から公共メディアへの転換を図っているが、こうした手法もEU構成国では標準的なものではない。むしろ、イギリスにおけるPublic Value Testや、ドイツにおけるDrei-Stufen-Testのように、近年では公共メディアのあり方に関する社会的コンセンサスの形成が重視されている。こうしたイタリアの議論からは、公共メディアについても国家に対する距離の確保と社会的コンセンサスの形成が重要となることを読み取ることができる。
令和2年度第1回法律研究会(報告者:永岩慧子)
| 日時 | 2020年11月25日(水)15時00分~16時30分 |
| 報告テーマ | 請負における結果の達成と請負人の責任−近時のドイツの議論を中心に |
| 報告者 | 永岩慧子(民法) |
2017年に成立し、2020年4月1日に施行された民法(債権法)改正法は、契約の場面における瑕疵の用語を、種類または品質に関して「契約の内容に適合しない」という表現に置き換え、瑕疵判断を契約の趣旨・解釈の問題とする。改正法の規定は、これまでの瑕疵判断の枠組みを変更するものではないとの見方が多数であるが、具体的な判断要素は条文に明記されず、個別の契約類型において、どのように契約内容を確定するかが問題となる。
請負の紛争の中心となっている建築契約では、設計図書・仕様書等を手がかりに瑕疵を判断するというのが基本的な考え方であるが、契約内容の複雑性に加え、工事開始後の仕様変更等も珍しくないことから、設計図書等が当事者の合意内容の確定において有力な拠り所とならない場合が多い。また、詳細な設計図書等がある場合でも、建築の素人である注文者がそれらに記載された個々の施工内容の意味を正確に把握することは困難である。さらに、請負契約の性質上、履行過程において仕事の完成までに生じうる不確定な要素をどのように調整するか、とりわけ請負人の労務に外在的な事情による結果不達成リスクの位置付けが問題になる。
この点、ドイツ法では、瑕疵がないとされるための判断要素が条文上規定されており、当事者の合意を第一としながらも、通常の使用適性といった客観的基準について、これを逸脱する合意がない限り確保されるべきであるとされている。ドイツにおいて請負に特徴的な問題として、当事者が合意した設計図書等に従って施工されたが、完成した建築物が契約で目的としていた機能を備えない場合、瑕疵があるとされるのかどうかが議論となっている。この問題に対し、ドイツ連邦通常裁判所は、注文者が契約で期待した機能を実現することが合意された契約目的であるとし、請負人は、それに向けられた給付義務を負うとする。このように広い瑕疵概念のもとで瑕疵責任の適用を認める判例理論に対して、学説上、注文者保護の観点から肯定的な評価が加えられている。
ドイツの議論から得られる視点として、まず、契約内容の確定をめぐる問題について、請負契約では、しばしば、個々の取り決めの総体として合意が形成され、これらの個々の内容が一定の結果の実現に向けられたものであるということ、また、素人たる注文者と専門的知識を有した請負人との関係性を考慮して、技術的・専門的な概念が多用された設計図書等の記述のみを拠り所とするのではなく、当該契約の目的に照らした解釈がなされる必要がある。次に、請負人の労務に外在的な事情による結果不達成と請負人の責任について、広い瑕疵概念のもと「請負人の結果達成義務の肯定+免責可能性」という構成を採用するドイツの判例法理は、当事者の知識の非対称性に加え、請負の履行段階と責任段階との連続性といった契約類型としての特徴を考慮したものと捉えることも可能である。なお、ドイツの判例法理については、救済手段における実質的な利点を強調するものがみられる一方、理論上の問題をめぐり議論が続けられている。わが国の理論上の課題と対比しながら今後の検討を進めたい。
請負の紛争の中心となっている建築契約では、設計図書・仕様書等を手がかりに瑕疵を判断するというのが基本的な考え方であるが、契約内容の複雑性に加え、工事開始後の仕様変更等も珍しくないことから、設計図書等が当事者の合意内容の確定において有力な拠り所とならない場合が多い。また、詳細な設計図書等がある場合でも、建築の素人である注文者がそれらに記載された個々の施工内容の意味を正確に把握することは困難である。さらに、請負契約の性質上、履行過程において仕事の完成までに生じうる不確定な要素をどのように調整するか、とりわけ請負人の労務に外在的な事情による結果不達成リスクの位置付けが問題になる。
この点、ドイツ法では、瑕疵がないとされるための判断要素が条文上規定されており、当事者の合意を第一としながらも、通常の使用適性といった客観的基準について、これを逸脱する合意がない限り確保されるべきであるとされている。ドイツにおいて請負に特徴的な問題として、当事者が合意した設計図書等に従って施工されたが、完成した建築物が契約で目的としていた機能を備えない場合、瑕疵があるとされるのかどうかが議論となっている。この問題に対し、ドイツ連邦通常裁判所は、注文者が契約で期待した機能を実現することが合意された契約目的であるとし、請負人は、それに向けられた給付義務を負うとする。このように広い瑕疵概念のもとで瑕疵責任の適用を認める判例理論に対して、学説上、注文者保護の観点から肯定的な評価が加えられている。
ドイツの議論から得られる視点として、まず、契約内容の確定をめぐる問題について、請負契約では、しばしば、個々の取り決めの総体として合意が形成され、これらの個々の内容が一定の結果の実現に向けられたものであるということ、また、素人たる注文者と専門的知識を有した請負人との関係性を考慮して、技術的・専門的な概念が多用された設計図書等の記述のみを拠り所とするのではなく、当該契約の目的に照らした解釈がなされる必要がある。次に、請負人の労務に外在的な事情による結果不達成と請負人の責任について、広い瑕疵概念のもと「請負人の結果達成義務の肯定+免責可能性」という構成を採用するドイツの判例法理は、当事者の知識の非対称性に加え、請負の履行段階と責任段階との連続性といった契約類型としての特徴を考慮したものと捉えることも可能である。なお、ドイツの判例法理については、救済手段における実質的な利点を強調するものがみられる一方、理論上の問題をめぐり議論が続けられている。わが国の理論上の課題と対比しながら今後の検討を進めたい。
令和元年度第1回法律研究会(報告者:三上正隆)
| 日時 | 2019年12月18日(水)15時10分~16時40分 |
| 報告テーマ | 愛護動物虐待関連犯罪をめぐる諸問題 |
| 報告者 | 三上正隆(刑法) |
動物愛護管理法令和元年改正において、同法44条に規定されている愛護動物虐待関連犯罪の法定刑が大幅に引き上げられた。特に、愛護動物殺傷罪の法定刑は懲役5年又は罰金500万円となり、同罪は例えば器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)よりも重大な犯罪となった。もっとも、愛護動物虐待関連犯罪は、行為客体が動物であることもあってか、これまで刑事法研究の分野において十分に目を向けられて来た犯罪であるとは言い難い。そこで、本報告では、同罪の概要を踏まえつつ、その諸問題(特に、①保護法益、②「虐待」の意義、③「遺棄」の意義)について検討を加える。
まず、①愛護動物虐待関連犯罪の保護法益は、「動物の生命・身体等、動物自身が有する利益」、「(将来危害が加えられ得る)人の生命・身体・財産」、「人の感情」といった利益であるとも考えられるが、動物愛護管理法の目的(1条)、同罪の行為客体が「愛護動物」とされていること、法における人間中心主義・人間中心主義的法益概念などに照らし、「動物愛護の良俗」であると解すべきである。次に、②愛護動物虐待罪における「虐待」の意義については、「残酷な取扱いをすること」と解する見解もあるが、同法2条記載の行為のうち、「苦しめる」は愛護動物虐待罪で捕捉されていると解することができる等の理由から、「強度な苦痛を与えること」と考えるべきである。次いで、③愛護動物遺棄罪における「遺棄」の意義については、「終生飼養義務違反(飼育放棄)」との理解もあり得るが、それでは努力義務である終生飼養義務(同法7条4項)が刑罰によって強制される法的義務に格上げされることになって不当であり、同罪の保護法益が「動物愛護の良俗」であることにかんがみれば、「愛護動物に対する危険の惹起」と解すべきである。
上記のように、解釈論上、愛護動物虐待関連犯罪の保護法益は、「動物愛護の良俗」であると解することができる。もっとも、立法論において、動物虐待関連犯罪の保護法益は、①動物は彼ら自身の資格において配慮に値するという意味での道徳的権利を有する、②「法益は人間関係的有用性を有する利益に限られる」と解する決定的な論拠は見出せず、人間関係的有用性を有さない、動物固有の利益である上記道徳的権利も法益と認める余地はある、③この法益は、刑罰による保護が正当化されるための要件(=比例原則)を備える、と考えることができることから、「人間の利益とは独立に存在する、動物の利益それ自体である」と解すべきである。
まず、①愛護動物虐待関連犯罪の保護法益は、「動物の生命・身体等、動物自身が有する利益」、「(将来危害が加えられ得る)人の生命・身体・財産」、「人の感情」といった利益であるとも考えられるが、動物愛護管理法の目的(1条)、同罪の行為客体が「愛護動物」とされていること、法における人間中心主義・人間中心主義的法益概念などに照らし、「動物愛護の良俗」であると解すべきである。次に、②愛護動物虐待罪における「虐待」の意義については、「残酷な取扱いをすること」と解する見解もあるが、同法2条記載の行為のうち、「苦しめる」は愛護動物虐待罪で捕捉されていると解することができる等の理由から、「強度な苦痛を与えること」と考えるべきである。次いで、③愛護動物遺棄罪における「遺棄」の意義については、「終生飼養義務違反(飼育放棄)」との理解もあり得るが、それでは努力義務である終生飼養義務(同法7条4項)が刑罰によって強制される法的義務に格上げされることになって不当であり、同罪の保護法益が「動物愛護の良俗」であることにかんがみれば、「愛護動物に対する危険の惹起」と解すべきである。
上記のように、解釈論上、愛護動物虐待関連犯罪の保護法益は、「動物愛護の良俗」であると解することができる。もっとも、立法論において、動物虐待関連犯罪の保護法益は、①動物は彼ら自身の資格において配慮に値するという意味での道徳的権利を有する、②「法益は人間関係的有用性を有する利益に限られる」と解する決定的な論拠は見出せず、人間関係的有用性を有さない、動物固有の利益である上記道徳的権利も法益と認める余地はある、③この法益は、刑罰による保護が正当化されるための要件(=比例原則)を備える、と考えることができることから、「人間の利益とは独立に存在する、動物の利益それ自体である」と解すべきである。
平成30年度第1回法律研究会(報告者:黒野葉子)
| 日時 | 2018年12月19日(水)15時10分~16時40分 |
| 報告テーマ | 親会社により選任された子会社取締役の忠実義務 |
| 報告者 | 黒野葉子(会社法) |
複数の会社が資本的に結合し、企業グループを形成して事業活動を行う場合、企業グループを構成する各会社は、自社の利益の最大化を目指す一方で、企業グループ全体の利益を最大化させるため、自らが属する企業グループにおける統一的な経営方針のもと、親会社等の経営指揮に沿った行為を行うことがある。そして、そのような企業グループの一体的経営を円滑に実現するために、親会社の役員が子会社の取締役を兼任したり、親会社の従業員が子会社の取締役に選任されたりするケースも少なくない。そのような、親会社から派遣された取締役に課される忠実義務は、その他の取締役のそれと同一であるのか。わが国の伝統的な法理論に基づけば、取締役は、自らが取締役となっている「当該会社の利益」のために行為しなければならず、親会社の利益やグループ全体の利益といった「当該会社(=子会社)の利益」以外の利益のために行為することは認められないと考えられてきた。しかし、親会社による統一的経営方針のもとにグループ経営が行われるケースでは、親会社により選任された子会社取締役に、常に自らの自由な判断のもとに子会社単体の利益の最大化を追求するよう期待することは難しい面もある。
この点、オーストラリア会社法は、「指名取締役(nominee director)」と呼ばれる「ある者の利益を代表するために選任された取締役」の会社に対する誠実義務に関して判例および学説上、議論を展開してきたが、1999年には、「完全子会社の取締役は(a)子会社の定款によって、親会社の最善の利益のために行為することが明示的に授権されており、(b)実際に親会社の最善の利益のために行為しており、かつ、(c)行為時に、子会社が支払不能状態ではなく、またその行為によって支払不能に陥らない場合には、子会社の最善の利益のために行為していたものとされる」旨の立法を行った。
オーストラリア会社法には、子会社債権者や子会社少数株主の保護に資する制度が複数用意されており、そのような制度が十分整備されていないわが国において、ただちにオーストラリア会社法と同様の立法や解釈を行うことには慎重でなければならないが、円滑なグループ経営の実現を目指すとき、オーストラリア会社法における指名取締役の誠実義務に関する議論は、法と現実の乖離を是正するものとして注目される。
この点、オーストラリア会社法は、「指名取締役(nominee director)」と呼ばれる「ある者の利益を代表するために選任された取締役」の会社に対する誠実義務に関して判例および学説上、議論を展開してきたが、1999年には、「完全子会社の取締役は(a)子会社の定款によって、親会社の最善の利益のために行為することが明示的に授権されており、(b)実際に親会社の最善の利益のために行為しており、かつ、(c)行為時に、子会社が支払不能状態ではなく、またその行為によって支払不能に陥らない場合には、子会社の最善の利益のために行為していたものとされる」旨の立法を行った。
オーストラリア会社法には、子会社債権者や子会社少数株主の保護に資する制度が複数用意されており、そのような制度が十分整備されていないわが国において、ただちにオーストラリア会社法と同様の立法や解釈を行うことには慎重でなければならないが、円滑なグループ経営の実現を目指すとき、オーストラリア会社法における指名取締役の誠実義務に関する議論は、法と現実の乖離を是正するものとして注目される。
平成28年度第1回法律研究会(報告者:髙橋洋)
| 日時 | 2016年12月7日15時10分~16時40分 |
| 報告テーマ | 立法裁量論をめぐって |
| 報告者 | 髙橋洋 |
裁判所が法律の違憲審査を行う際に、立法府の政策判断に敬意を払い、法律の目的や目的達成手段の詳細な検討を行ったり、裁判所独自の判断を示すのは控えるべきだという立法裁量論という議論がある。この議論は判例によって形成されてきたものである。
学説は、立法裁量論によって裁判所の違憲審査権が後退し、その分人権保障の後退が起きている点を問題視し、立法裁量論の適用領域を限定したり、裁量統制をはかる理論形成を試みてきた。現時点においても、立法裁量論に依拠して合憲判決を導く判例は少なくないが、多くの領域で従来の判例を明示的・黙示的に変更し、立法裁量論から離脱する判例が出てきており、潮目が変わったと思われる。以下では、こうした兆候を示す判例の動向をフォローするとともに、学説における動向も整理してみたい。
まず、立法裁量論にかかわる判例としては、①議員定数配分不均衡、②公務員の労働基本権、③生存権、④財産権規制、⑤職業の自由の規制、⑥家族・婚姻制度、⑦国家賠償制度に関するものがある。これらの事例についての検討から、全体として立法裁量論が縮小に向かっていることが読みとれる。このことは近年の最高裁における司法審査の活性化傾向と合致している。
つぎに、学説については、近年の立法裁量論を限定しようとする枠組みとして、立法者の自己拘束の追求、ベースライン論、制度後退禁止原則、判断過程審査、制度的保障(制度体保障)などがある。それぞれの議論にも課題があるため、今後とも検討していきたい。
学説は、立法裁量論によって裁判所の違憲審査権が後退し、その分人権保障の後退が起きている点を問題視し、立法裁量論の適用領域を限定したり、裁量統制をはかる理論形成を試みてきた。現時点においても、立法裁量論に依拠して合憲判決を導く判例は少なくないが、多くの領域で従来の判例を明示的・黙示的に変更し、立法裁量論から離脱する判例が出てきており、潮目が変わったと思われる。以下では、こうした兆候を示す判例の動向をフォローするとともに、学説における動向も整理してみたい。
まず、立法裁量論にかかわる判例としては、①議員定数配分不均衡、②公務員の労働基本権、③生存権、④財産権規制、⑤職業の自由の規制、⑥家族・婚姻制度、⑦国家賠償制度に関するものがある。これらの事例についての検討から、全体として立法裁量論が縮小に向かっていることが読みとれる。このことは近年の最高裁における司法審査の活性化傾向と合致している。
つぎに、学説については、近年の立法裁量論を限定しようとする枠組みとして、立法者の自己拘束の追求、ベースライン論、制度後退禁止原則、判断過程審査、制度的保障(制度体保障)などがある。それぞれの議論にも課題があるため、今後とも検討していきたい。
平成26年度第2回法律研究会(報告者:野村健太郎)
| 日時 | 2014年7月16日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 量刑「理論」の意義と限界 |
| 報告者 | 野村健太郎(刑法) |
裁判員裁判の導入等を契機として、量刑の基準を明確な「言葉」で示すことの必要性が強く意識されるようになった。この量刑の「理論化」においては、実務感覚を言語化する作業とともに、その感覚の正当性を刑法理論に照らして検証する作業が必要となる。刑法理論においては、①構成要件該当性、②違法性、③有責性(責任)が犯罪成立の要件とされている(犯罪論体系)。このうち、量刑の基準として応用可能なのは、②および③であり、②「違法性の程度」および③「責任の程度」に応じて、刑の量を決めるべきだと考えられている(そのようにして導かれた刑の枠内で、予防的な考慮を働かせる余地は残される)。
もっとも、このような「理論化」の作業は、量刑上の考慮を過度に制約することで、かえって公正さを欠いた帰結をもたらす危険をも孕んでいる。例えば、しばしば裁判実務においては、捜査機関による違法行為が刑の軽減事由として考慮されてきたが、行為者の「責任」の重さにとってそのような事情が意味を持たないとすれば、その考慮は理論的には正当化し難いことになる。しかし、かかる考慮の余地を一律に排除することが妥当かについては、疑問が残る。このような、一見すると刑法理論上正当化し得ないように思える考慮について、その必要性が強く感じられる場合には、理論的枠組みの内容そのものを再考することにより、理論的正当化の可能性を探るべきであるように思われる。上記の例に関していえば、量刑を決める「責任」には、責任を問われる行為者に関わる事情のみならず、責任を問う国家(機関)に関わる事情も影響し得るのではないかが、検討に値しよう。
このようにして構築される量刑理論は、そこから直ちに具体的な刑量を導けるようなものではない。最終的な判断は、判断者(裁判官・裁判員)の「感覚」に大きく依存せざるを得ない(そこでは、他の裁判の集積から読み取れる量刑の「相場」ないし「傾向」も重要な意味を持つ)。ここに、「理論化」の限界がある。しかし、このような理論的枠組みが存在することにより、判断者は、どのような「感覚」をどのように働かせてよいか、また、働かせるべきかについて、一定の指針を得ることができる。このように、量刑を「理論化」することには、限られた、しかし、確かな意義を見出すことができるのである。
もっとも、このような「理論化」の作業は、量刑上の考慮を過度に制約することで、かえって公正さを欠いた帰結をもたらす危険をも孕んでいる。例えば、しばしば裁判実務においては、捜査機関による違法行為が刑の軽減事由として考慮されてきたが、行為者の「責任」の重さにとってそのような事情が意味を持たないとすれば、その考慮は理論的には正当化し難いことになる。しかし、かかる考慮の余地を一律に排除することが妥当かについては、疑問が残る。このような、一見すると刑法理論上正当化し得ないように思える考慮について、その必要性が強く感じられる場合には、理論的枠組みの内容そのものを再考することにより、理論的正当化の可能性を探るべきであるように思われる。上記の例に関していえば、量刑を決める「責任」には、責任を問われる行為者に関わる事情のみならず、責任を問う国家(機関)に関わる事情も影響し得るのではないかが、検討に値しよう。
このようにして構築される量刑理論は、そこから直ちに具体的な刑量を導けるようなものではない。最終的な判断は、判断者(裁判官・裁判員)の「感覚」に大きく依存せざるを得ない(そこでは、他の裁判の集積から読み取れる量刑の「相場」ないし「傾向」も重要な意味を持つ)。ここに、「理論化」の限界がある。しかし、このような理論的枠組みが存在することにより、判断者は、どのような「感覚」をどのように働かせてよいか、また、働かせるべきかについて、一定の指針を得ることができる。このように、量刑を「理論化」することには、限られた、しかし、確かな意義を見出すことができるのである。
平成26年度第1回法律研究会(報告者:佐藤啓子)
| 日時 | 2014年5月25日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 遺産分割と共有物分割 |
| 報告者 | 佐藤啓子(民法) |
共有物分割と遺産分割の比較と「棲み分け」は、従来より論じられてきたテーマである。一見すると、相続という特殊な理由から発生する共有にはそれに適した解消方法があり、それと一般的な共有の解消方法とが対置されているように見える。また、通常裁判所の管轄する共有物分割が原則であり、遺産分割は家庭裁判所の管轄する特別な手続であると明快に考えることも可能かもしれない。そして、日本の相続法は立法時にドイツ法よりもむしろフランス法から多くの影響を受けており、そのフランス法における遺産の位置づけからも、遺産分割は例外的な手続という結論が導かれやすく思われる。
それにもかかわらずこの点が絶えず論じられてきた理由には、そのような考え方の妥当性に対する問題意識がある。通常の共有とされる場合であっても相続と類縁の原因による場合が多いと推測される(たとえば最判平成25.11.29民集67巻8号1736頁は会社と相続人との共有を解消しようとする事例だが、その会社の代表者は相続人の一人である。また森林法違憲判決として知られる最大判昭和62.4.22民集41巻3号408頁は、相続分前渡しの事例であった。)。しかし、近似しているにもかかわらずその手続には大きな違いがある。たとえば相続人の一人が特定の相続財産の自己の持分を売却した場合、その共有財産の分割は遺産分割手続ではなく共有物分割手続に服し、その場合、他の相続人は905条により買戻すことはできないと解されている(最判昭和53.7.13判例時報908号41頁)。
相続前の事情については、原因の多様性・当事者の意思を考えると如何ともしがたい。ただ、そもそも最高裁判所を頂点とする実務は、可分債権・可分債務は原則的に相続開始時に分割済みとして扱い(民法427条を根拠とする)、また遺産分割する前の相続不動産の賃料債権も相続分で帰属させるなど、遺産分割の対象にならない遺産を多く認めており、すでにそれが具体的相続分の実現を困難ならしめている。その上、一人の相続人が、自己の相続財産の一部処分により、特定の相続財産を遺産分割の対象から外すことができる。この現状は、その相続人(あるいはその者と親しい相続人たち)に遺産分割をさらに空洞化する権限を認めることにつながりかねない。
それでは日本法の母法であるフランス法も同様の制度であるかというと、特定相続財産の持分権譲渡については、実は日本と異なった様相が見えてくる。フランス民法にはそもそも、日本の母法となる買戻権が規定されていたがそれは削除された。しかしその代わり、他の相続人の先買権制度が導入された。すなわち、ある相続人が遺産分割されていない財産の(全部または)一部を相続人以外の者に譲渡する場合には、事前にその旨ほかの相続人に通知しなければならず、通知を受けた相続人は1か月以内に先買権を行使することができる。これにより、相続財産の一部が相続人以外の者に属する事態、ひいては遺産分割の対象から外される事態を防ぐことが可能である(フランス民法815条の14)。
そもそも個々の相続人による個別財産の持分権譲渡を認めるべきではなかったと筆者は考えているが、遺産分割に時間制限がないことから、遺産の一部でよいから早く現金化したいと希望する相続人は少なくないことも認めざるをなえない。ただ、金銭的価値のある遺産ほど遺産分割から外れていき、ほかの相続人はそれを傍観するしかないという現行解釈は、いかがなものかと思われる。第三者保護も確かに重要であるが、譲受人は自分の譲り受けた財産は遺産の一部であったということを知っていたはずであり、遺産分割の適正化の要請がより重要であると考える。
それにもかかわらずこの点が絶えず論じられてきた理由には、そのような考え方の妥当性に対する問題意識がある。通常の共有とされる場合であっても相続と類縁の原因による場合が多いと推測される(たとえば最判平成25.11.29民集67巻8号1736頁は会社と相続人との共有を解消しようとする事例だが、その会社の代表者は相続人の一人である。また森林法違憲判決として知られる最大判昭和62.4.22民集41巻3号408頁は、相続分前渡しの事例であった。)。しかし、近似しているにもかかわらずその手続には大きな違いがある。たとえば相続人の一人が特定の相続財産の自己の持分を売却した場合、その共有財産の分割は遺産分割手続ではなく共有物分割手続に服し、その場合、他の相続人は905条により買戻すことはできないと解されている(最判昭和53.7.13判例時報908号41頁)。
相続前の事情については、原因の多様性・当事者の意思を考えると如何ともしがたい。ただ、そもそも最高裁判所を頂点とする実務は、可分債権・可分債務は原則的に相続開始時に分割済みとして扱い(民法427条を根拠とする)、また遺産分割する前の相続不動産の賃料債権も相続分で帰属させるなど、遺産分割の対象にならない遺産を多く認めており、すでにそれが具体的相続分の実現を困難ならしめている。その上、一人の相続人が、自己の相続財産の一部処分により、特定の相続財産を遺産分割の対象から外すことができる。この現状は、その相続人(あるいはその者と親しい相続人たち)に遺産分割をさらに空洞化する権限を認めることにつながりかねない。
それでは日本法の母法であるフランス法も同様の制度であるかというと、特定相続財産の持分権譲渡については、実は日本と異なった様相が見えてくる。フランス民法にはそもそも、日本の母法となる買戻権が規定されていたがそれは削除された。しかしその代わり、他の相続人の先買権制度が導入された。すなわち、ある相続人が遺産分割されていない財産の(全部または)一部を相続人以外の者に譲渡する場合には、事前にその旨ほかの相続人に通知しなければならず、通知を受けた相続人は1か月以内に先買権を行使することができる。これにより、相続財産の一部が相続人以外の者に属する事態、ひいては遺産分割の対象から外される事態を防ぐことが可能である(フランス民法815条の14)。
そもそも個々の相続人による個別財産の持分権譲渡を認めるべきではなかったと筆者は考えているが、遺産分割に時間制限がないことから、遺産の一部でよいから早く現金化したいと希望する相続人は少なくないことも認めざるをなえない。ただ、金銭的価値のある遺産ほど遺産分割から外れていき、ほかの相続人はそれを傍観するしかないという現行解釈は、いかがなものかと思われる。第三者保護も確かに重要であるが、譲受人は自分の譲り受けた財産は遺産の一部であったということを知っていたはずであり、遺産分割の適正化の要請がより重要であると考える。
平成25年度第1回法律研究会(報告者:小林明夫)
| 日時 | 2013年10月30日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 自治立法の企画立案過程についての一考察~国の省庁との比較から |
| 報告者 | 小林明夫(行政法) |



本報告は、政策法務組織論に係るものである。
この報告では、自治体の条例の中でもその大宗を占める首長提案条例について、その制定過程のうちの「議会前過程」(執行部による条例案の企画立案)にスポットを当てつつ、首長提案条例を中心とする自治立法の企画立案過程はいかなるもので、そして今後どうあるべきかについて、国法(閣法・政省令等)の企画立案過程との比較・分析という観点から検討した。
この報告では、自治体の条例の中でもその大宗を占める首長提案条例について、その制定過程のうちの「議会前過程」(執行部による条例案の企画立案)にスポットを当てつつ、首長提案条例を中心とする自治立法の企画立案過程はいかなるもので、そして今後どうあるべきかについて、国法(閣法・政省令等)の企画立案過程との比較・分析という観点から検討した。
まず、条例案の企画立案に係る一般的な流れと国法の企画立案過程とをそれぞれ概観してみると、後者は、大きく省庁内過程と政府内過程とに分化している点、そこから導かれる内閣法制局予備審査や各省協議の存在、ややインフォーマルな与党内過程の存在など前者にはない複雑な構造を成していることがその特色である。
そして、これらのうち、法令審査のシステムに着目すると、原課内での審査、原局総務課での審査(部局内審査)、大臣官房における審査(官房審査)、内閣法制局予備審査という具合に、省庁内過程と政府内過程に跨がって、かつ、省庁内過程単独で見ても、「複層的な審査体制」が存在することが、国のシステムの大きな特徴となっている。
上記の複層的な審査体制のうち、官房審査の段階を例にとってその質的な面をみてみると、これは立案に当たる原局側と審査に当たる官房側との徹底した議論の場として機能している。このことは、国法の立案・審査システムの質的特徴であり、自治体の法規審査にはあまり見られない点である。一般に自治体の法規審査において、原課は法制部課に対して比較的従順であり、法制部課との間で議論まで闘わせることは少ない。そもそも法制担当セクションが行う「法規の審査」とは、「制定後に当該法規の運用を担うべき原部局原課側の立案行為に対して法制的観点から問題点を指摘し、それを乗り越えようとする立案担当者と討論を行うことによって、当該法規案が法制的に適正かつ妥当なものになるよう導いていく一連の作用」のことである。この概念を前提に考えれば、そこには文字どおり「討論」というプロセスが不可欠なはずである。また、一般に法は、不特定多数の受範者・事案に適用されるものであるため、一定の客観性や普遍性が要求されることから、その立案過程においては特に法制面からの批判的な検討が不可欠であるということもできよう。
このように討論が必要であるとして、では実際に、官房審査の場における活発な討論を可能にしているものは一体何であろうか。一つは、「審査する側と審査を受ける側の法的知識のレベルが拮抗していること」も勿論であるが、それだけでなく、さきほど指摘した「複層的な審査体制」の存在と無縁ではないものと考えられる。
報告者は、法規審査の構造を、政策立法を指向する立案側のベクトル(「政策立法指向ベクトル」)と問題点を指摘する審査側のベクトル(「審査ベクトル」)との相剋という形で捉え、これを法規生成システムの基本原理と位置づける。このベクトル相剋論を前提にして分析すると、官房審査に前置されている部局内審査を了した際、その段階での審査ベクトルは政策立法指向ベクトルに新たに取り込まれ、次の官房審査の段階では部局側の政策立法指向ベクトルの一部となって作動するというメカニズムが存在する。このような仕組みにより、ベクトルの相剋が次々と連鎖し、しかも増幅した形で発生していくことになる。
国の立法システムには、複層的な審査体制や審査の場が「討論」の場となっていることなど伝統的に自治体にはない長所があることは以上に述べたとおりである。首長提案条例の企画立案過程のあり方、ひいては、「より良き自治立法システム」を考えていく際には、こういった点を参考に、研究していくことが大切と考える。要は、多段階で「ベクトルの相剋」が起こる仕組みが自治立法システムにビルトインされているか、あるいはこれをどうビルトインしていくのか。そして、そのような自治立法システムの行程に載せるべき事案か否かを判断する基準とその判断を行う場はどうするのか、といった点が重要なポイントになろう。
他方、その際には、機動力、市民参加的手法、立法の契機が市民的視点・生活者の視点に近い、といった地方自治の有するアドバンテージを十分意識した上で、より良き自治立法システムを研究・構想していくことが妥当なのではないかと考えている。
そして、これらのうち、法令審査のシステムに着目すると、原課内での審査、原局総務課での審査(部局内審査)、大臣官房における審査(官房審査)、内閣法制局予備審査という具合に、省庁内過程と政府内過程に跨がって、かつ、省庁内過程単独で見ても、「複層的な審査体制」が存在することが、国のシステムの大きな特徴となっている。
上記の複層的な審査体制のうち、官房審査の段階を例にとってその質的な面をみてみると、これは立案に当たる原局側と審査に当たる官房側との徹底した議論の場として機能している。このことは、国法の立案・審査システムの質的特徴であり、自治体の法規審査にはあまり見られない点である。一般に自治体の法規審査において、原課は法制部課に対して比較的従順であり、法制部課との間で議論まで闘わせることは少ない。そもそも法制担当セクションが行う「法規の審査」とは、「制定後に当該法規の運用を担うべき原部局原課側の立案行為に対して法制的観点から問題点を指摘し、それを乗り越えようとする立案担当者と討論を行うことによって、当該法規案が法制的に適正かつ妥当なものになるよう導いていく一連の作用」のことである。この概念を前提に考えれば、そこには文字どおり「討論」というプロセスが不可欠なはずである。また、一般に法は、不特定多数の受範者・事案に適用されるものであるため、一定の客観性や普遍性が要求されることから、その立案過程においては特に法制面からの批判的な検討が不可欠であるということもできよう。
このように討論が必要であるとして、では実際に、官房審査の場における活発な討論を可能にしているものは一体何であろうか。一つは、「審査する側と審査を受ける側の法的知識のレベルが拮抗していること」も勿論であるが、それだけでなく、さきほど指摘した「複層的な審査体制」の存在と無縁ではないものと考えられる。
報告者は、法規審査の構造を、政策立法を指向する立案側のベクトル(「政策立法指向ベクトル」)と問題点を指摘する審査側のベクトル(「審査ベクトル」)との相剋という形で捉え、これを法規生成システムの基本原理と位置づける。このベクトル相剋論を前提にして分析すると、官房審査に前置されている部局内審査を了した際、その段階での審査ベクトルは政策立法指向ベクトルに新たに取り込まれ、次の官房審査の段階では部局側の政策立法指向ベクトルの一部となって作動するというメカニズムが存在する。このような仕組みにより、ベクトルの相剋が次々と連鎖し、しかも増幅した形で発生していくことになる。
国の立法システムには、複層的な審査体制や審査の場が「討論」の場となっていることなど伝統的に自治体にはない長所があることは以上に述べたとおりである。首長提案条例の企画立案過程のあり方、ひいては、「より良き自治立法システム」を考えていく際には、こういった点を参考に、研究していくことが大切と考える。要は、多段階で「ベクトルの相剋」が起こる仕組みが自治立法システムにビルトインされているか、あるいはこれをどうビルトインしていくのか。そして、そのような自治立法システムの行程に載せるべき事案か否かを判断する基準とその判断を行う場はどうするのか、といった点が重要なポイントになろう。
他方、その際には、機動力、市民参加的手法、立法の契機が市民的視点・生活者の視点に近い、といった地方自治の有するアドバンテージを十分意識した上で、より良き自治立法システムを研究・構想していくことが妥当なのではないかと考えている。
平成24年度第1回法律研究会(報告者:前田太朗)
| 日時 | 2012年12月19日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | オーストリアにおける危険責任法理の展開と限界 |
| 報告者 | 前田太朗(民法) |


本報告は、「オーストリアにおける危険責任法理の展開と限界」と題して、過失責任と危険責任との各責任原理間の関係性を、オーストリアの危険責任論の展開を見ることで検討するものである。過失責任は、公害や製造物責任等の企業による事業活動に伴って生じる大規模事故を処理するために、厳格な予見義務、結果回避義務を問題とする責任原理となった。事案の解決に役立つとしても理論的に見れば、もはや過失責任とは言えない「過失の衣を着た無過失」責任へと過失責任が変容することとなった。
他方で、こうした過失責任による無過失責任の欠缺補充は、本来は危険責任によるものであり、ドイツ法での展開を比較法の対象とされる。しかし、危険責任が一般的に認められるようになることで、過失責任は変容することになるのか。危険性の強弱のみで両者の関係性を見るとしてもその射程は必ずしも明らかではなく、両責任原理の関係性は依然として不明確である。とくに解釈論から立法論へと視点を移した時に、両責任原理そしてそれに関係する他の責任原理との関係性が一定程度明確ではなく、不明確であれば、立法後の法発展、実務に影響を及ぼす。
この問題意識に対して重大な示唆を与えるのがオーストリア法である。同法では、一方で過失責任は主観的に解され、他方で、危険責任が類推適用により拡張的に用いられる。両責任原理の関係性がそこで一見したところ明確に区別されている。
オーストリアにおいて危険責任法理の展開が必要であったのは、オーストリア一般民法典(ABGB)11315条に規定される使用者責任の射程が狭いこと及び過失責任の発展がそれほど見られないことにあった。こうした法状況において、危険責任の展開に大きな影響をあたえたのは、Armin Ehrenzweigであった。彼は、填補がなければ許されない活動は、填補がなされていればその活動は認めるべきであり、しかし、その事業活動により伴う危険性が実現し損害を惹起するならば、その事業活動を行う者は、損害賠償責任を負うとして、ここでは、立法の遅さ、使用者責任の狭隘さ、使用者責任規定の厳格な適用の問題を挙げて、危険な事情活動を行う事業者への危険責任をひろく適用することを主張し、これに基づいて、オーストリア最高裁(OGH)も、危険責任を拡張して適用してきた。しかし、ここでは危険責任の類推といっても、各事件、各制定法から基本思想を導き出し、それを具体的な事件に当てはめて解決するのではなく(大きな解決)、制定法として規定された危険責任を個別に慎重に類推して適用し、事件を解決していく方向性を、OGHは明確に示している(小さな解決)。
また危険責任以外に目を転じても、契約責任による処理、機関を広くとらえ法人の責任を認める代表者責任の展開により、危険責任だけではなく、総合的にこれらの法理により、事業活動に伴って生じる事故の処理を行ってきた。
ここで本報告の問題意識に基づいて比較法をまとめるならば、危険責任は類推適用によってもそこまでの射程を持つものではないということが、明確になり、そうだあれば、これを補完する責任原理なり法理が必要となる。そして責任原理間の関係性を考えていく上では、単に危険性の強度だけではなく、それ以外の特徴、性質を見出すべきと考えている。
他方で、こうした過失責任による無過失責任の欠缺補充は、本来は危険責任によるものであり、ドイツ法での展開を比較法の対象とされる。しかし、危険責任が一般的に認められるようになることで、過失責任は変容することになるのか。危険性の強弱のみで両者の関係性を見るとしてもその射程は必ずしも明らかではなく、両責任原理の関係性は依然として不明確である。とくに解釈論から立法論へと視点を移した時に、両責任原理そしてそれに関係する他の責任原理との関係性が一定程度明確ではなく、不明確であれば、立法後の法発展、実務に影響を及ぼす。
この問題意識に対して重大な示唆を与えるのがオーストリア法である。同法では、一方で過失責任は主観的に解され、他方で、危険責任が類推適用により拡張的に用いられる。両責任原理の関係性がそこで一見したところ明確に区別されている。
オーストリアにおいて危険責任法理の展開が必要であったのは、オーストリア一般民法典(ABGB)11315条に規定される使用者責任の射程が狭いこと及び過失責任の発展がそれほど見られないことにあった。こうした法状況において、危険責任の展開に大きな影響をあたえたのは、Armin Ehrenzweigであった。彼は、填補がなければ許されない活動は、填補がなされていればその活動は認めるべきであり、しかし、その事業活動により伴う危険性が実現し損害を惹起するならば、その事業活動を行う者は、損害賠償責任を負うとして、ここでは、立法の遅さ、使用者責任の狭隘さ、使用者責任規定の厳格な適用の問題を挙げて、危険な事情活動を行う事業者への危険責任をひろく適用することを主張し、これに基づいて、オーストリア最高裁(OGH)も、危険責任を拡張して適用してきた。しかし、ここでは危険責任の類推といっても、各事件、各制定法から基本思想を導き出し、それを具体的な事件に当てはめて解決するのではなく(大きな解決)、制定法として規定された危険責任を個別に慎重に類推して適用し、事件を解決していく方向性を、OGHは明確に示している(小さな解決)。
また危険責任以外に目を転じても、契約責任による処理、機関を広くとらえ法人の責任を認める代表者責任の展開により、危険責任だけではなく、総合的にこれらの法理により、事業活動に伴って生じる事故の処理を行ってきた。
ここで本報告の問題意識に基づいて比較法をまとめるならば、危険責任は類推適用によってもそこまでの射程を持つものではないということが、明確になり、そうだあれば、これを補完する責任原理なり法理が必要となる。そして責任原理間の関係性を考えていく上では、単に危険性の強度だけではなく、それ以外の特徴、性質を見出すべきと考えている。
平成22年度第2回法律研究会(報告者:村上康司)
| 日時 | 2010年12月22日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 企業買収における取締役の責任はどうあるべきか |
| 報告者 | 村上康司(商法) |
90年代後半から株式持合いの解消が進み、海外機関投資家の持株比率増加による敵対的買収の脅威から、買収防衛策を採用する企業が増加し、買収防衛策をめぐる法的問題点が次々と明らかになり、実務上も明確なルールの存在を求められるようになった。しかし、国内の状況を見てみると、①企業買収に関するルールの整備状況は必ずしも十分とは言えず、②買収防衛策にあたり、どの機関がどのような役割を担うべきかについても確定的な考えがあるわけではない。
①の問題点については、「企業価値報告書」や、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の公表により、一定のルール作りへの取り組みがなされ、裁判例においても、不公正発行に関するいわゆる「主要目的ルール」を足掛かりとして、いくつかの事例において、解決策が図られてきている。他方、②の問題については、様々な見解が対立しており、その問題は、企業買収において、取締役が防衛策を講ずることができるのか、できるのであればどのような条件・内容であるのが望ましいのかという点に集約される。この問題は、企業買収の局面において買収防衛策が必要であるか否かは、経営事項について情報と見分を有する取締役が判断することができ、取締役の判断が不合理であったため、株主が損害を被ることがあるとすれば、事後的にその損害賠償を取締役に対して追及することにより、取締役の行為を規律付けることができると考えられる。
この場合の、取締役に対する責任追及に際して、企業買収に関する判例の蓄積が相当程度みられ、我が国の近時の議論も強く影響を受けていると思われるアメリカ法においては、不利益を生じた株主が、取締役に対して直接的に責任請求しうる。EUにおいても、企業買収に関するルール作りへの取り組みがみられ、ドイツにおいては、株主による取締役への直接的な責任追及が認容される場合は、我が国において会社の支配権につき争いのある場合に、不公正発行を行うケースなどと局面が類似している。
これらの考察を通じて、取締役への責任追及にあたっては、取締役側に、防衛策が不合理なものではなかったことの挙証責任が課されるべきであると考えられる。買収防衛策として取締役が採った行為について、合理性が認められるのであれば、それは取締役の損害賠償責任の追及において、違法性阻却事由として考慮すべきである。ただし、株主総会の決議を得ていたとしても、買収防衛策の必要性についての司法審査を排除すべきではなかろう。損害額の確定については、どの時点を起算点として画定していくかについて、さらなる検討が必要である。
①の問題点については、「企業価値報告書」や、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の公表により、一定のルール作りへの取り組みがなされ、裁判例においても、不公正発行に関するいわゆる「主要目的ルール」を足掛かりとして、いくつかの事例において、解決策が図られてきている。他方、②の問題については、様々な見解が対立しており、その問題は、企業買収において、取締役が防衛策を講ずることができるのか、できるのであればどのような条件・内容であるのが望ましいのかという点に集約される。この問題は、企業買収の局面において買収防衛策が必要であるか否かは、経営事項について情報と見分を有する取締役が判断することができ、取締役の判断が不合理であったため、株主が損害を被ることがあるとすれば、事後的にその損害賠償を取締役に対して追及することにより、取締役の行為を規律付けることができると考えられる。
この場合の、取締役に対する責任追及に際して、企業買収に関する判例の蓄積が相当程度みられ、我が国の近時の議論も強く影響を受けていると思われるアメリカ法においては、不利益を生じた株主が、取締役に対して直接的に責任請求しうる。EUにおいても、企業買収に関するルール作りへの取り組みがみられ、ドイツにおいては、株主による取締役への直接的な責任追及が認容される場合は、我が国において会社の支配権につき争いのある場合に、不公正発行を行うケースなどと局面が類似している。
これらの考察を通じて、取締役への責任追及にあたっては、取締役側に、防衛策が不合理なものではなかったことの挙証責任が課されるべきであると考えられる。買収防衛策として取締役が採った行為について、合理性が認められるのであれば、それは取締役の損害賠償責任の追及において、違法性阻却事由として考慮すべきである。ただし、株主総会の決議を得ていたとしても、買収防衛策の必要性についての司法審査を排除すべきではなかろう。損害額の確定については、どの時点を起算点として画定していくかについて、さらなる検討が必要である。
平成22年度第1回法律研究会(報告者:三上正隆)
| 日時 | 2010年6月23日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 犯罪論体系と規範理論 |
| 報告者 | 三上正隆(刑法) |
ドイツ刑法学においては、カール・ビンディングがその精緻な研究により、規範と刑罰法規とを分離・対置して規範理論を基礎付けて以来、同理論は今日に至るまで、重要な地位を占め続けてきた。これに対して、我が国の刑法学において規範理論は、まず主観的違法論と客観的違法論の対立において重要な役割を担い、客観的違法論が勝利を収めた後には、客観的違法論内部での結果無価値論と行為無価値論の対立において、議論の中軸にあったと言える。しかし、結果無価値論を支えた「モラリズムの排斥」という命題が浸透するにつれ、規範概念の使用が回避されるようになり、規範理論はその地位を低下させていったのである。もっとも、近時、行為無価値論と結果無価値論の対立が深化乃至止揚の段階に入り、不法構造論に論争の場が移行するにつれ、規範理論は再び注目されるようになって来ている。
規範理論が現在の刑法学において注目に値する理由は、同理論が犯罪体系論及び刑法解釈論の双方に対して小さからぬ意義を有していることに求めることができよう。すなわち、一般に、犯罪は①構成要件該当性②違法性③有責性という三要件をすべて備えたものをいうと考えられているが、各要件の関係は必ずしも明らかなものとは言えない。この点、違法及び責任の各段階に属する規範の捉え方いかんによって、各要件の関係は影響を受け、その影響が犯罪論体系全体にまで及ぶものと考え得る。ここから、規範理論は犯罪論体系を整序する意義を有していると解することができる。また、「対物防衛」「責任無能力者に対する正当防衛」「同意傷害の可罰性」「未遂犯における危険の判断基準」などといった刑法解釈論上の論点は、違法段階に属する規範の「機能・名宛人」「淵源」「規範違反の内実」といった視座からこれを検討することが可能であり、規範理論は刑法解釈論の基礎となり得るものであると考えられる。
もっとも、現在の我が国の刑法学においては、論者ごとにその用いる規範概念の内容等が異なり、規範理論それ自体を議論する共通の土俵が存在しているとは言い難い。そこで、まずは、規範の「機能・名宛人」「淵源」「規範違反の内実」といった視座から、これまで用いられてきた規範概念(及び規範理論)を整理・分析し、上記土俵を形成する必要があろう。その後、形成された土俵の上で、犯罪論体系の構築及び刑法解釈論の展開において指針となり得るような規範理論を作り上げていくべきものと解される。
規範理論が現在の刑法学において注目に値する理由は、同理論が犯罪体系論及び刑法解釈論の双方に対して小さからぬ意義を有していることに求めることができよう。すなわち、一般に、犯罪は①構成要件該当性②違法性③有責性という三要件をすべて備えたものをいうと考えられているが、各要件の関係は必ずしも明らかなものとは言えない。この点、違法及び責任の各段階に属する規範の捉え方いかんによって、各要件の関係は影響を受け、その影響が犯罪論体系全体にまで及ぶものと考え得る。ここから、規範理論は犯罪論体系を整序する意義を有していると解することができる。また、「対物防衛」「責任無能力者に対する正当防衛」「同意傷害の可罰性」「未遂犯における危険の判断基準」などといった刑法解釈論上の論点は、違法段階に属する規範の「機能・名宛人」「淵源」「規範違反の内実」といった視座からこれを検討することが可能であり、規範理論は刑法解釈論の基礎となり得るものであると考えられる。
もっとも、現在の我が国の刑法学においては、論者ごとにその用いる規範概念の内容等が異なり、規範理論それ自体を議論する共通の土俵が存在しているとは言い難い。そこで、まずは、規範の「機能・名宛人」「淵源」「規範違反の内実」といった視座から、これまで用いられてきた規範概念(及び規範理論)を整理・分析し、上記土俵を形成する必要があろう。その後、形成された土俵の上で、犯罪論体系の構築及び刑法解釈論の展開において指針となり得るような規範理論を作り上げていくべきものと解される。
平成21年度第2回法律研究会(報告者:府川繭子)
| 日時 | 2010年1月13日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | フランスにおける立法国賠訴訟の検討 |
| 報告者 | 府川繭子(行政法) |
本報告では、フランス行政法のEU法への統合過程において生じた問題の一つである、立法行為に起因する損害の国家賠償について、いかなる議論が行われ、どのようなかたちで判例上決着が図られたのかを検討した。
フランスにおいては、法律に対する上位規範違反の審査が長らく行われてこなかった。それゆえ、上位規範違反の法律によって生じた損害の国家賠償訴訟自体が想定できない状況にあった。ところが、行政裁判所において法律の条約適合性審査が開始されたこと、およびEC裁判所(現EU裁判所)が加盟国の国内法がEU法に違反することによって生じた損害の賠償を義務付けたことにより、フランスにおいても、上位規範たる条約に違反する立法行為を原因行為とする賠償訴訟が現実の問題として議論されるようになった。
フランスにおいては、国家賠償責任はフォート(違法・過失)による責任とフォートによらない責任(適法・無過失)に分けられる。そこで、条約違反の立法行為をフォートによる責任の枠組みにおいて解決するのか、フォートによらない責任による枠組みで解決するのかが大きな論点となった。通常の行政行為については、上位規範違反=フォートという定式が判例上確立しており、フォートによる責任の枠組みにおいて賠償が行われている。学説の多数は、原因行為が立法行為である場合にも、行政行為に関する上記の定式を適用し、法律の上位規範違反=フォートであると理解し、条約違反の立法国賠の問題をフォートによる責任の枠組みにおいて扱う立場を支持した。しかし、他方で、条約違反の立法国賠をフォートによる責任の枠組みにおいて処理することは、立法者がフォートを犯した(違法な行為を行った)ことを意味するため、一般意思の表明としての法律というテーゼの下で法律及び立法者が特別な地位を占めてきたフランス行政法においてはなお受け入れがたい側面があった。
この問題について、フランスの行政裁判所は、まず、条約違反の法律と損害との間に、法律の適用行為として行われた行政行為が介在している場合には、行政行為の違法を理由として国家賠償を認容するという解決を行い、立法者のフォートへの言及を避けた。こうした行政行為への責任の転嫁は、行政裁判所は立法者のフォートを認めることに強い抵抗を感じていたことを示すものといえる。このような状況の中で、特殊な立法形態をとる法律が問題となったために、法律と損害との間に他の行為が介在しない事案が、行政裁判所に提訴された。この事案において、行政裁判所は、立法者のフォートを認めるか否かという問題に正面から対峙することとなった。結論としては、行政裁判所は、条約違反の立法行為に起因する損害の賠償訴訟を通常の枠組みとは異なる独自の制度を打ち立てることで対応した。すなわち、フォートによる責任でもフォートによらない責任でもない、法律の条約違反それ自体による責任という新たな枠組みを設けたのである。行政裁判所が、立法者のフォートの承認という一線は譲らなかったものの、既存の国家賠償法理の枠外で立法国賠の問題を処理するほかなかったことは、既存の国内法理とEU法との間で行政裁判所が厳しい判断を迫られたことを示している。
行政裁判所が上記のような解決法を採るに際して行った説明およびそれに影響を与えた学説を検討すると、この解決法が非常に形式的かつ便宜的な説明に基づいていることが伺える。もはや便宜的にしか対応できない程度にフランス国内法のEU法への統合は進んでいる。同時に、フランスにおいて長い間タブーとされてきた立法者のフォートの承認が、学説において公然と主張され、しかもそれが多数説となったことも、EU法の影響の大きさを表しているといえる。
フランスにおいては、法律に対する上位規範違反の審査が長らく行われてこなかった。それゆえ、上位規範違反の法律によって生じた損害の国家賠償訴訟自体が想定できない状況にあった。ところが、行政裁判所において法律の条約適合性審査が開始されたこと、およびEC裁判所(現EU裁判所)が加盟国の国内法がEU法に違反することによって生じた損害の賠償を義務付けたことにより、フランスにおいても、上位規範たる条約に違反する立法行為を原因行為とする賠償訴訟が現実の問題として議論されるようになった。
フランスにおいては、国家賠償責任はフォート(違法・過失)による責任とフォートによらない責任(適法・無過失)に分けられる。そこで、条約違反の立法行為をフォートによる責任の枠組みにおいて解決するのか、フォートによらない責任による枠組みで解決するのかが大きな論点となった。通常の行政行為については、上位規範違反=フォートという定式が判例上確立しており、フォートによる責任の枠組みにおいて賠償が行われている。学説の多数は、原因行為が立法行為である場合にも、行政行為に関する上記の定式を適用し、法律の上位規範違反=フォートであると理解し、条約違反の立法国賠の問題をフォートによる責任の枠組みにおいて扱う立場を支持した。しかし、他方で、条約違反の立法国賠をフォートによる責任の枠組みにおいて処理することは、立法者がフォートを犯した(違法な行為を行った)ことを意味するため、一般意思の表明としての法律というテーゼの下で法律及び立法者が特別な地位を占めてきたフランス行政法においてはなお受け入れがたい側面があった。
この問題について、フランスの行政裁判所は、まず、条約違反の法律と損害との間に、法律の適用行為として行われた行政行為が介在している場合には、行政行為の違法を理由として国家賠償を認容するという解決を行い、立法者のフォートへの言及を避けた。こうした行政行為への責任の転嫁は、行政裁判所は立法者のフォートを認めることに強い抵抗を感じていたことを示すものといえる。このような状況の中で、特殊な立法形態をとる法律が問題となったために、法律と損害との間に他の行為が介在しない事案が、行政裁判所に提訴された。この事案において、行政裁判所は、立法者のフォートを認めるか否かという問題に正面から対峙することとなった。結論としては、行政裁判所は、条約違反の立法行為に起因する損害の賠償訴訟を通常の枠組みとは異なる独自の制度を打ち立てることで対応した。すなわち、フォートによる責任でもフォートによらない責任でもない、法律の条約違反それ自体による責任という新たな枠組みを設けたのである。行政裁判所が、立法者のフォートの承認という一線は譲らなかったものの、既存の国家賠償法理の枠外で立法国賠の問題を処理するほかなかったことは、既存の国内法理とEU法との間で行政裁判所が厳しい判断を迫られたことを示している。
行政裁判所が上記のような解決法を採るに際して行った説明およびそれに影響を与えた学説を検討すると、この解決法が非常に形式的かつ便宜的な説明に基づいていることが伺える。もはや便宜的にしか対応できない程度にフランス国内法のEU法への統合は進んでいる。同時に、フランスにおいて長い間タブーとされてきた立法者のフォートの承認が、学説において公然と主張され、しかもそれが多数説となったことも、EU法の影響の大きさを表しているといえる。
平成21年度第1回法律研究会(報告者:鈴木慎太郎)
| 日時 | 2009年6月17日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 臓器は所有の対象か?-臓器売買をめぐる法・倫理・政策- |
| 報告者 | 鈴木慎太郎(法哲学) |
臓器移植医療が社会的に受容されるためには、移植用臓器が公正に配分される制度が必要である。わが国において、臓器のあっせんは、社団法人日本臓器移植ネットワークが一元的に担っている。しかし、臓器の配分を一元的に行うのではなく、私的な決定に委ねるという発想もありえ、現にそのような提案を行う者も存在する。この考えをさらに進めるならば、臓器の私的な取引、すなわち臓器売買によって臓器の配分問題を解決する、という選択肢もありうることになる。欧米の法学者、倫理学者の一部には、臓器売買を認めるべきである、との見解をもつ者が存在する。ただし、わが国を含め、世界の法制に目を向けるならば、臓器売買は禁止すべきものとされている。本報告では、臓器売買禁止論と容認論のそれぞれについて、説得的な根拠があるか否かを検討し、臓器売買についての正しい制度的対応のあり方を探究する。
臓器売買の禁止は国際的な趨勢である。しかし、その禁止の根拠は不明確である。臓器売買禁止の根拠としては、人々の感情に著しく反すること、移植機会の公平性を損なうこと、善意・任意の臓器提供という臓器移植の基本的な考え方に支障を来すこと、国民の信頼確保という公共的利益のため、「人」を「物」に転化させないため、社会的な負の反応への対処のためなどが考えられている。しかし、そのいずれもが、詳細に検討されたならば、臓器売買統制の根拠になりうるかもしれないが、臓器売買を全面的に禁止することの根拠としては十分な説得力を有する根拠とは言い難いものばかりである。
臓器売買容認論を十分に説得的な根拠を有しているだろうか。臓器売買を容認する者は、医療上の正当防衛、契約の自由、臓器売買を認めた場合の臓器提供量増加の予測モデル、政治道徳の多元性などを根拠に臓器売買の正当化を試みている。しかし、これらの根拠についても、それぞれに難点があり、いずれも、臓器売買を容認する議論として、決定的な説得力をもつとは言い難い。
このように、臓器売買をめぐる議論は、禁止論も容認論も決定的な議論を提出できておらず、直ちに決着をつけることが難しい状況にある、というのが報告者の見解である。しかし、このような状況にあってもなお、臓器売買を禁止するのか容認するのかの制度的な決定をなさなければならない。そこで提案したいのが、臓器売買に関する「制度の初期設定」は何か、の探究である。すなわち、「原則として臓器は売買の対象ではない」と考えるべきか、「原則として臓器は売買の対象である」と考えるべきかを問う、というものである。かりに、制度の初期設定が決まれば、禁止論も容認論も決定的とはいえない状況においては、初期設定をそのまま採用する、という制度選択が可能になると考える。それでは、その初期設定はどのように探究すべきか。その方法については、未だ明確なものがあるとは言えず、探究方法そのものを、試行錯誤的に探究しなければならない。ひとつの可能性として、近代法制度が根幹にもつと考える政治道徳を解釈し、それともっとも整合的な考え方を初期設定とする、ということが考えられる。この方法が有効であり、臓器についてのどのような法的扱いをすることが初期設定と考えるべきかについては今後の課題である。
臓器売買の禁止は国際的な趨勢である。しかし、その禁止の根拠は不明確である。臓器売買禁止の根拠としては、人々の感情に著しく反すること、移植機会の公平性を損なうこと、善意・任意の臓器提供という臓器移植の基本的な考え方に支障を来すこと、国民の信頼確保という公共的利益のため、「人」を「物」に転化させないため、社会的な負の反応への対処のためなどが考えられている。しかし、そのいずれもが、詳細に検討されたならば、臓器売買統制の根拠になりうるかもしれないが、臓器売買を全面的に禁止することの根拠としては十分な説得力を有する根拠とは言い難いものばかりである。
臓器売買容認論を十分に説得的な根拠を有しているだろうか。臓器売買を容認する者は、医療上の正当防衛、契約の自由、臓器売買を認めた場合の臓器提供量増加の予測モデル、政治道徳の多元性などを根拠に臓器売買の正当化を試みている。しかし、これらの根拠についても、それぞれに難点があり、いずれも、臓器売買を容認する議論として、決定的な説得力をもつとは言い難い。
このように、臓器売買をめぐる議論は、禁止論も容認論も決定的な議論を提出できておらず、直ちに決着をつけることが難しい状況にある、というのが報告者の見解である。しかし、このような状況にあってもなお、臓器売買を禁止するのか容認するのかの制度的な決定をなさなければならない。そこで提案したいのが、臓器売買に関する「制度の初期設定」は何か、の探究である。すなわち、「原則として臓器は売買の対象ではない」と考えるべきか、「原則として臓器は売買の対象である」と考えるべきかを問う、というものである。かりに、制度の初期設定が決まれば、禁止論も容認論も決定的とはいえない状況においては、初期設定をそのまま採用する、という制度選択が可能になると考える。それでは、その初期設定はどのように探究すべきか。その方法については、未だ明確なものがあるとは言えず、探究方法そのものを、試行錯誤的に探究しなければならない。ひとつの可能性として、近代法制度が根幹にもつと考える政治道徳を解釈し、それともっとも整合的な考え方を初期設定とする、ということが考えられる。この方法が有効であり、臓器についてのどのような法的扱いをすることが初期設定と考えるべきかについては今後の課題である。
平成20年度第2回法律研究会(報告者:武田典浩)
| 日時 | 2008年10月29日(水) 15:10~ |
| 報告テーマ | 会社倒産状況における取締役の責任-会社法と倒産法の交錯- |
| 報告者 | 武田典浩(商法) |
会社の経営危機状況において、取締役・支配社員により会社財産が食いつぶされたり、リスクの高い取引を行って損失を拡大させたりすることにより会社が倒産した場合、会社債権者はこのような取引を行った取締役等の責任を追及することによって、自己の利益が守られます。この責任追及手段は時に、倒産手続と競合することがあります。会社法における取締役の責任追及手段を採ると、個別の債権者が他の債権者に先んじて債権の満足に与ることができます。その一方、倒産手続における取締役の責任追及によると会社財団の増殖が目され、債権者はその財団から債権額に応じて平等に割当を受けるだけにすぎません。
このような、一部の債権者に優先的に満足を受けさせることを許容する、会社法のルールは、会社倒産状況においても果たして妥当させるべきしょうか。倒産手続と類似の手続に変容させて、債権者が平等に満足を受けさせるような責任制度に変容させる必要があるのでしょうか。
アメリカ法においては、近時の裁判例により、上記状況における取締役の責任追及を個別債権者の満足のためではなく、会社財団を増殖させる方向に舵を切りました。これは、取締役の責任の趣旨を倒産法と類似のものであることを認めたためです。
ドイツにおいては、取締役の責任追及を会社財団増殖の方向に性質決定する裁判例はまだないようです。ただ、少数ながら近時の学説においては、会社財産増殖の方向性に変更すべきであるとの見解もあります。また、ドイツにおける、支配社員の責任追及については、近時の最高裁判所判決において、会社財団増殖の方向に変化してきています。しかし、取締役の責任に関する近時の学説も、また、支配社員の責任に関する最高裁判決も、会社財団増殖の方向へと変化することを望む理由は、ヨーロッパ法を牽引する地位にあるイギリス法の真似をするという観点が全面的に強調されています。よって、理論的な検討は不十分であるとさえ言えます。
日本法においては、会社法429条による取締役の第三者責任が債権者による個別的責任追及手段として機能しているため、これを倒産法類似の責任制度へと再構成する必要があるかもしれません。しかし、どの国の法律を参照とすべきかは難問です。かねてより、上記アメリカ・ドイツ法を参照して、会社法 429条(旧商法266条の3)責任を再構成しようとする動きがあります。ただ、理論的に詰められていないドイツ法を参照すると、場合によっては論点の履き違いにもなりかねません。また、アメリカ法において倒産法にいかなる期待をかけているのか(クラスアクションのような大規模責任追及手段)を見逃してしまうと、やはり論点の履き違いになる恐れがあります。比較法を行う態度は、かなり慎重である必要があるといえましょう。
このような、一部の債権者に優先的に満足を受けさせることを許容する、会社法のルールは、会社倒産状況においても果たして妥当させるべきしょうか。倒産手続と類似の手続に変容させて、債権者が平等に満足を受けさせるような責任制度に変容させる必要があるのでしょうか。
アメリカ法においては、近時の裁判例により、上記状況における取締役の責任追及を個別債権者の満足のためではなく、会社財団を増殖させる方向に舵を切りました。これは、取締役の責任の趣旨を倒産法と類似のものであることを認めたためです。
ドイツにおいては、取締役の責任追及を会社財団増殖の方向に性質決定する裁判例はまだないようです。ただ、少数ながら近時の学説においては、会社財産増殖の方向性に変更すべきであるとの見解もあります。また、ドイツにおける、支配社員の責任追及については、近時の最高裁判所判決において、会社財団増殖の方向に変化してきています。しかし、取締役の責任に関する近時の学説も、また、支配社員の責任に関する最高裁判決も、会社財団増殖の方向へと変化することを望む理由は、ヨーロッパ法を牽引する地位にあるイギリス法の真似をするという観点が全面的に強調されています。よって、理論的な検討は不十分であるとさえ言えます。
日本法においては、会社法429条による取締役の第三者責任が債権者による個別的責任追及手段として機能しているため、これを倒産法類似の責任制度へと再構成する必要があるかもしれません。しかし、どの国の法律を参照とすべきかは難問です。かねてより、上記アメリカ・ドイツ法を参照して、会社法 429条(旧商法266条の3)責任を再構成しようとする動きがあります。ただ、理論的に詰められていないドイツ法を参照すると、場合によっては論点の履き違いにもなりかねません。また、アメリカ法において倒産法にいかなる期待をかけているのか(クラスアクションのような大規模責任追及手段)を見逃してしまうと、やはり論点の履き違いになる恐れがあります。比較法を行う態度は、かなり慎重である必要があるといえましょう。
平成20年度第1回法律研究会(報告者:石田倫識)
| 日時 | 2008年6月25日(水) 17:00~ |
| 報告テーマ | 黙秘権保障の歴史と到達点 |
| 報告者 | 石田倫識(刑事訴訟法) |
刑事被告人・被疑者の黙秘権は、今日では、広く知れ渡った権利であり、国際社会においても、確固たる権利として広く承認されている(例えば、自由権規約14条3項(g)等)。ところが、現実には、この権利は実質的に保障されているとは言い難い。とりわけ、犯罪の多発化、捜査の困難化がいわれる現代にあって、諸外国においても、むしろこの権利を限定ないし制限する方向での立法や判例が出てきている。
例えば、黙秘権の母国と評されるイギリスにおいても、1994年に黙秘権を制限する法律が制定されている。この法律は一定の条件のもとに、黙秘の事実から、不利益な推認を導くことを許容したものであった。また、ドイツにおいても、一部黙秘については、不利益な推認を許すのが判例の立場とされている。
日本においては、今日においても、判例上、黙秘からの不利益推認は許されていない。しかしながら、近年、黙秘権行使を助言する弁護活動に対する批判がなされたり、また、黙秘権が行使された事例において、検察官が黙秘からの不利益推認を主張するという事態も生じており、黙秘権の存在意義を疑問視する声も聞かれるところである。
諸外国において、黙秘権を限定ないし制限する方向での立法・判例が出され始めた背景には、「弁護人による援助を受ける権利が実質化し、被疑者取調べに対する規制・監視も強まって、今日では、黙秘権の存在意義は失われつつあるのではないか」との意識があるように思われる。この点、我が国でも同様の傾向がみられる。すなわち、90年代における当番弁護士制度の樹立、2004年の刑訴法改正で創設された被疑者段階からの国選弁護制度等、一定程度、被疑者・被告人の権利保障が拡充されつつあり、それに伴って、黙秘権の存在意義は失われつつあるとの認識・理解があるように思われる。そして、このような理解は、被疑者・被告人に対する弁護権保障や被疑者取調べに対する法的規制の充実が予測される将来においては、ますます強まってくるのではないだろうか。
しかしながら、弁護権保障の拡充が達成され、被疑者取調べに対する法的規制が充実してくれば、本当に黙秘権はその存在意義を失ってしまうのか。黙秘権には、弁護権保障の拡充等によってもなおカバーしきれない、独自の存在意義が存するのではないだろか。黙秘権保障の問題は、個人の権利保障と国家の捜査権限との間の適正なバランスを如何にして確保するかという問題でもあり、適当な解決を図るのが非常に難しい局面の一つではある。しかし、少なくとも、犯罪対策という現代的要請から安易な制限論へと傾斜する前に、今一度、黙秘権の発祥・発展の歴史的過程の検証・分析を通じ、改めて黙秘権の存在意義、存在理由ないし存在根拠が確認されるべきではないだろうか。
例えば、黙秘権の母国と評されるイギリスにおいても、1994年に黙秘権を制限する法律が制定されている。この法律は一定の条件のもとに、黙秘の事実から、不利益な推認を導くことを許容したものであった。また、ドイツにおいても、一部黙秘については、不利益な推認を許すのが判例の立場とされている。
日本においては、今日においても、判例上、黙秘からの不利益推認は許されていない。しかしながら、近年、黙秘権行使を助言する弁護活動に対する批判がなされたり、また、黙秘権が行使された事例において、検察官が黙秘からの不利益推認を主張するという事態も生じており、黙秘権の存在意義を疑問視する声も聞かれるところである。
諸外国において、黙秘権を限定ないし制限する方向での立法・判例が出され始めた背景には、「弁護人による援助を受ける権利が実質化し、被疑者取調べに対する規制・監視も強まって、今日では、黙秘権の存在意義は失われつつあるのではないか」との意識があるように思われる。この点、我が国でも同様の傾向がみられる。すなわち、90年代における当番弁護士制度の樹立、2004年の刑訴法改正で創設された被疑者段階からの国選弁護制度等、一定程度、被疑者・被告人の権利保障が拡充されつつあり、それに伴って、黙秘権の存在意義は失われつつあるとの認識・理解があるように思われる。そして、このような理解は、被疑者・被告人に対する弁護権保障や被疑者取調べに対する法的規制の充実が予測される将来においては、ますます強まってくるのではないだろうか。
しかしながら、弁護権保障の拡充が達成され、被疑者取調べに対する法的規制が充実してくれば、本当に黙秘権はその存在意義を失ってしまうのか。黙秘権には、弁護権保障の拡充等によってもなおカバーしきれない、独自の存在意義が存するのではないだろか。黙秘権保障の問題は、個人の権利保障と国家の捜査権限との間の適正なバランスを如何にして確保するかという問題でもあり、適当な解決を図るのが非常に難しい局面の一つではある。しかし、少なくとも、犯罪対策という現代的要請から安易な制限論へと傾斜する前に、今一度、黙秘権の発祥・発展の歴史的過程の検証・分析を通じ、改めて黙秘権の存在意義、存在理由ないし存在根拠が確認されるべきではないだろうか。
平成19年度第3回法律研究会(報告者:伊藤栄寿)
| 日時 | 2007年10月17日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 区分所有における所有法理と団体法理 ―ドイツ住居所有権法の近時の議論を参考に- |
| 報告者 | 伊藤栄寿(民法) |
区分所有建物(いわゆるマンション)は、現在、500万戸以上存在し、1000万人以上が居住している。今後は、築30年以上の老朽化マンションが加速度的に増加すると予測されており、2011年には、100万戸以上が老朽化マンションとして存在することとなるといわれている。そこで、2002年、マンションの法律関係を定める「建物の区分所有等に関する法律」の大改正が行われた。とりわけ、1995年の阪神淡路大震災における建替えの困難を教訓とし、老朽化マンション対策として、新しい建替え決議制度が設けられた。従来、マンションを建替えるためには、建物(マンション)の効用を維持するために過分の費用がかかることが必要であり(「客観的要件」とよばれる)、さらに、区分所有者・議決権の各5分の4以上の賛成が必要であるとされていた。2002 年に改正された法律は、前者の客観的要件を削除し、後者の、区分所有者・議決権の各5分の4以上の賛成により、建替えを行うことができるとした。
この改正法は、従来に比べ、マンションの建替えを行いやすくしたとして、一定の評価を与えることができる。しかしながら、他方で、分譲マンションにおいて、多くの者が「建替えを行いたい」と考えた場合には、少数の高齢者などが「建替えを行う資金がないため、修繕を行いながら、可能な限りこのままマンションに住み続けたい」と考えても、多数者の意見が尊重され、建替えは実行されることになる。その結果、少数者のマンションに対する所有権(区分所有権)が、時価により、多数者により剥奪されることになる。
分譲マンションを購入したという場合、購入者は自己の専有部分に対する「所有権」を取得することになるが、同時に、管理組合などの団体に属し、団体構成員として活動を行うことにもなる。後者の点に着目し、マンションの所有者(区分所有者)の権利は、団体に対する権利だとする考え方もある。しかしながら、日本の建物区分所有法の沿革や一般人の考え方を尊重すると、マンション購入者の権利はあくまで「所有権」である。
したがって、団体構成員だとして、限界なくマンション所有者の権利を制限することは許されず、個別の場面ごとに、所有権であることをどこまで修正することができるのを検討する必要があると考えられる。たとえば、建替え決議の場面であれば、区分所有者・議決権の各5分の4以上の賛成があれば、常に当然に建替えが正当化されると考えるのではなく、あまりにも建替えの費用負担が大きく、かつ、少数者の居住権が害される場合には、建替え決議は無効となる、と考えるべきではないだろうか。
この改正法は、従来に比べ、マンションの建替えを行いやすくしたとして、一定の評価を与えることができる。しかしながら、他方で、分譲マンションにおいて、多くの者が「建替えを行いたい」と考えた場合には、少数の高齢者などが「建替えを行う資金がないため、修繕を行いながら、可能な限りこのままマンションに住み続けたい」と考えても、多数者の意見が尊重され、建替えは実行されることになる。その結果、少数者のマンションに対する所有権(区分所有権)が、時価により、多数者により剥奪されることになる。
分譲マンションを購入したという場合、購入者は自己の専有部分に対する「所有権」を取得することになるが、同時に、管理組合などの団体に属し、団体構成員として活動を行うことにもなる。後者の点に着目し、マンションの所有者(区分所有者)の権利は、団体に対する権利だとする考え方もある。しかしながら、日本の建物区分所有法の沿革や一般人の考え方を尊重すると、マンション購入者の権利はあくまで「所有権」である。
したがって、団体構成員だとして、限界なくマンション所有者の権利を制限することは許されず、個別の場面ごとに、所有権であることをどこまで修正することができるのを検討する必要があると考えられる。たとえば、建替え決議の場面であれば、区分所有者・議決権の各5分の4以上の賛成があれば、常に当然に建替えが正当化されると考えるのではなく、あまりにも建替えの費用負担が大きく、かつ、少数者の居住権が害される場合には、建替え決議は無効となる、と考えるべきではないだろうか。
平成19年度第2回法律研究会(報告者:鈴木伸智)
| 日時 | 2007年6月27日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 同性のカップルに対する法的保護のあり方-アメリカ合衆国における議論を中心に- |
| 報告者 | 鈴木伸智(民法) |
同性愛者とは、自分と同じ性の者を性愛の対象とする者のことです。異性愛者が、異性の者を性愛の対象とするのと同じように、同性愛者も同性の者を性愛の対象とします。ところが、異性愛者には、異性の者と結婚をすることが認められているのに、同性愛者には、同性の者と結婚をすることが認められていませんでした。現在では、オランダを始めとする数カ国で、同性同士で結婚をすること(「同性婚」といいます)が認められていますが、日本では、認められていません。
この問題について、アメリカ合衆国では、活発な議論が繰り広げられています。初めて裁判になったのは、1970年代のことです。当時は、「結婚は男女間でするもの」とされ、同性婚は認められませんでした。その後、「同性愛者が親になったら子どもに悪影響を及ぼすのではないか?」などの点が指摘され、現在、いくつかの州では、憲法によって、同性婚が禁止されています。一方、マサチューセッツ州では、結婚の定義を、「他の者を排除する二人の者の結合」と改め、同性のカップルもこれに含まれるとして、2004年5月17日に、同性婚を認めています。その他、同性のカップルに結婚は認めないものの、結婚をした夫婦と同じように扱うという制度(「シビル・ユニオン」といいます)を設けている州もあります。このように、同性のカップルへの対応は州によってさまざまです。
同性婚は、とくに一般の人々の間では、話題になっていないと思います。しかし、日本にも、同性婚をしたいと願うカップルが存在するのです。日本の法が、同性のカップルを赤の他人として扱うのか、何らかの保護を与えるのか、それとも、同性婚を認めるのか?今後、注目すべき課題の一つといえるでしょう。
この問題について、アメリカ合衆国では、活発な議論が繰り広げられています。初めて裁判になったのは、1970年代のことです。当時は、「結婚は男女間でするもの」とされ、同性婚は認められませんでした。その後、「同性愛者が親になったら子どもに悪影響を及ぼすのではないか?」などの点が指摘され、現在、いくつかの州では、憲法によって、同性婚が禁止されています。一方、マサチューセッツ州では、結婚の定義を、「他の者を排除する二人の者の結合」と改め、同性のカップルもこれに含まれるとして、2004年5月17日に、同性婚を認めています。その他、同性のカップルに結婚は認めないものの、結婚をした夫婦と同じように扱うという制度(「シビル・ユニオン」といいます)を設けている州もあります。このように、同性のカップルへの対応は州によってさまざまです。
同性婚は、とくに一般の人々の間では、話題になっていないと思います。しかし、日本にも、同性婚をしたいと願うカップルが存在するのです。日本の法が、同性のカップルを赤の他人として扱うのか、何らかの保護を与えるのか、それとも、同性婚を認めるのか?今後、注目すべき課題の一つといえるでしょう。
平成19年度第1回法律研究会(報告者:神田桂)
| 日時 | 2007年5月23日(水)15:10~ |
| 報告テーマ | 老後扶養を伴う財産移転と情誼関係の破綻 -フランス法上のbail à nourritureに見る負担不履行と当事者間不和の区分の検討から- |
| 報告者 | 神田 桂(民法) |
老後の面倒をみてもらうこと(老後扶養)を約束したり期待したりして、親世代から子世代への財産移転(贈与契約など)がなされたけれども、財産をあげた人(贈与者)と財産をもらった人(受贈者)の仲が悪くなってしまったような場合、贈与者はあげた財産を取り戻すことができるのでしょうか。
日本民法は既にあげてしまった財産についてはなかったことにして取り戻す(撤回する)ことはできないとしています(民法550条)。しかし裁判所は、既にあげてしまった財産についても、受贈者の忘恩行為または「老後扶養」負担の不履行が認定されるときには、贈与契約をなかったことにして財産を取り戻すことができるとしています(最判昭和53年2月17日参照)。ということは、逆に言うと、贈与者と受贈者が単に仲が悪くなってしまったというだけでは、いったんあげてしまった財産を取り戻すことはできないということになります(千葉地佐原支判平成7年6月27日参照)。
このような場合、贈与者と受贈者の仲が悪くなったこと(情誼関係の破綻)を理由として、贈与者が財産を取り戻すことを認めてあげるという解決方法を考えることもできます。しかしその場合には、民法の考え方によると、贈与者はいったんあげた財産を取り戻すことと引き換えに、あげた財産の見返りとしてそれまでに受け取ってきた「老後扶養」利益を受贈者に返さないといけないことになります。つまりこの解決方法は、(贈与者が受け取ってきた「老後扶養」利益を返すための十分な資力がない場合など)時には適切な解決方法とならない可能性も想定されます。
そこで「老後扶養」とは一体どのようなものかもう一度考え直してみると、「老後扶養」関係とは、そもそもその性質上必然的に長期間にわたる(贈与者と受贈者は長く「老後扶養」関係に拘束される)ことから、仲が悪くなるなどの当事者間の状況変化を不可避的に内包するものであると言えそうです。また近年わが国において所有不動産を利用した老後の経済的自立促進の動向(リバースモーゲージ制度の促進、または証券化によるリスク分散を付した日本型の終身定期金付不動産売買契約モデルの提示等)が存在しています。
ということは、当事者間の状況変化を不可避的に内包する「老後扶養」を伴う財産移転関係において、状況変化に即した柔軟な解決可能性を探るためには、「終身定期金rente viagère」契約(金銭給付)と「終身扶養契約bail à nourriture」(面倒見などの現物給付)のように、「老後扶養」関係を契約的に考えることが今後必要となってくるのではないでしょうか。このように考えることで、贈与者と受贈者の仲が悪くなってしまったような場合に、今までとは違った別の解決方法を採用したり、またはそのような事態に備えてあらかじめ契約を準備しておくことも可能になるのではないかと考えています。
日本民法は既にあげてしまった財産についてはなかったことにして取り戻す(撤回する)ことはできないとしています(民法550条)。しかし裁判所は、既にあげてしまった財産についても、受贈者の忘恩行為または「老後扶養」負担の不履行が認定されるときには、贈与契約をなかったことにして財産を取り戻すことができるとしています(最判昭和53年2月17日参照)。ということは、逆に言うと、贈与者と受贈者が単に仲が悪くなってしまったというだけでは、いったんあげてしまった財産を取り戻すことはできないということになります(千葉地佐原支判平成7年6月27日参照)。
このような場合、贈与者と受贈者の仲が悪くなったこと(情誼関係の破綻)を理由として、贈与者が財産を取り戻すことを認めてあげるという解決方法を考えることもできます。しかしその場合には、民法の考え方によると、贈与者はいったんあげた財産を取り戻すことと引き換えに、あげた財産の見返りとしてそれまでに受け取ってきた「老後扶養」利益を受贈者に返さないといけないことになります。つまりこの解決方法は、(贈与者が受け取ってきた「老後扶養」利益を返すための十分な資力がない場合など)時には適切な解決方法とならない可能性も想定されます。
そこで「老後扶養」とは一体どのようなものかもう一度考え直してみると、「老後扶養」関係とは、そもそもその性質上必然的に長期間にわたる(贈与者と受贈者は長く「老後扶養」関係に拘束される)ことから、仲が悪くなるなどの当事者間の状況変化を不可避的に内包するものであると言えそうです。また近年わが国において所有不動産を利用した老後の経済的自立促進の動向(リバースモーゲージ制度の促進、または証券化によるリスク分散を付した日本型の終身定期金付不動産売買契約モデルの提示等)が存在しています。
ということは、当事者間の状況変化を不可避的に内包する「老後扶養」を伴う財産移転関係において、状況変化に即した柔軟な解決可能性を探るためには、「終身定期金rente viagère」契約(金銭給付)と「終身扶養契約bail à nourriture」(面倒見などの現物給付)のように、「老後扶養」関係を契約的に考えることが今後必要となってくるのではないでしょうか。このように考えることで、贈与者と受贈者の仲が悪くなってしまったような場合に、今までとは違った別の解決方法を採用したり、またはそのような事態に備えてあらかじめ契約を準備しておくことも可能になるのではないかと考えています。